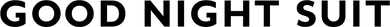Over the Counter ~中村暁野さんとコーヒー片手にエシカルトーク~ 1/3

今年2025年にはブランド創立から10周年を迎え、昨年2024年には神奈川県・藤野駅前に店舗をオープン。
GOOD NIGHT SUITの10年の道のりの中には、パジャマブランドとして、またアパレル業界の一員として、様々なシフトや大きな決断を迫られた時がありました。
単にオーガニックコットンにこだわるだけじゃない、心を包みこむ本当に優しいパジャマ作りへの想いを、先月コラボレーションパジャマ AKATSUKI ONE PIECE ORGANIC COTTON PAJAMASが発売となった、文筆家で<家族と一年商店>の店主・中村暁野さんと一緒に、GOOD NIGHT SUIT SHOPのカウンター越しにコーヒー片手にお話ししました。
==========================================

暁野(以後 A): そもそも、オーガニックコットンのブランドを立ち上げたきっかけは?
智有(以後 T) : 前職で日本の生地を海外に売る仕事をしていたんですけど、海外出張の度に、かっこいいパジャマブランドに沢山出会って。日本に帰ってきたら、かっこいい!と思えるパジャマブランドは当時はほぼ無い状態だったんです。それで、生地にこだわったかっこいいパジャマのブランドを作りたい!と思って始まったのがGOOD NIGHT SUIT(以後 GNS)です。
*より詳しいGNSの誕生秘話については、過去ログのコチラを是非ご覧ください。4話仕立てです。

※創業して間もなく、伊勢丹三越さんでポップアップをさせていただいた時のお写真です。
A : 2015年が創業だから、そのころは若い人はTshirtにスウェットみたいな格好で寝るのが当たり前、という感じだよね。そんな中でかっこいいパジャマへの情熱を抱いてから、すぐに日本でもやってみようと思ったのかな?
T : 親友がハワイで結婚式をあげるので、1週間休みください!と嘘をついて、初めて作ったパジャマを持ってROOMSという展示会に出たのが始まりですね。まさかの同僚がブースにやってきた時は、手伝ってくれていた父を前に立てて僕は隠れました(笑)。
その時、運よく伊勢丹三越さんやBEAMSさんとの取引が決まったんですけど、委託販売となると手数料の多さで予期せぬ大赤字。軌道に乗るまで、ローソンで唐揚げくんを揚げながら、パジャマをなんとか作り続けていましたね。

※ブランドを立ち上げて一番最初のコレクションの中の1着です。
A : 当初のパジャマはどんな感じだったの?
T : 当時はもっと派手派手な感じでしたね。シルエットもかなりスリムでタイト、格好良さを追求したブランドでした。ですが、「眠るための正装 ~GOOD NIGHT SUIT ~」というコンセプトとブランド名は既にこの頃からありました。
A : パジャマを作ってもらう工場などは、どうやって見つけたの?
T : 元々生地に関わる業界にいたので、そういう知識や経験をもとにパジャマも縫える縫製工場を自分で見つけたりしましたが、仕上がって来る商品のクオリティに問題が沢山あって、検品に相当な時間を費やしましたね。思い切って縫製工場を変えて、僕の地元の岐阜で見つけた縫製工場さんで再スタートしました。でも最初は発注数も少なくて、最初は工場の方もなかなかうちの商品を縫うことに慣れなかったので大変でした。今はやっと安定した縫製の綺麗さがあります。
A : 国内で作りたい、日本の生地を使いたい、という想いは最初からあったの?
T : 前職でたくさんの生地屋さんが廃業するのをみてきました。また、後継者不足の問題と外国産の安い生地の流通による国産生地の売り上げの低下に皆さん本当に悩んでましたね。どんどんといい生地屋さんが潰れていきました。だからこそ自分がブランドを立ち上げるときは絶対彼らと仕事をしたいと思っていたんです。made in JAPANへの想いは、かなり強かったです。
A: made in JAPANの服って、本当に少ないよね。
T: いや、本当に。国内で販売している全体の服のうち、現在僅か1. 5%ほどなんです。生地も縫製もmade in JAPANというのはそれぐらいしかない。そして国産のオーガニックコットンはほぼないですね。手間暇の割に、採れる量はとても少ないのが理由だと思います。
当初、僕は、とにかく、着心地第一、そして日本の生地を使って日本の生地業界を守る、日本の技術を次世代に後継する!ということをミッションに掲げてパジャマを作っていました。有難いことに、少しづつ軌道に乗っていきましたね。
きっかけは、ひとりの言葉

※2018年秋、鎌田安里紗さんがオフィスに遊びに来てくださいました。
A : 当時は国産生地にこだわっていて、まだオーガニックコットンではなかったんだよね?どういうきっかけでオーガニックコットンでパジャマを作り始めたのか一番気になるな。
T : GNSのパジャマの知名度が少しづつ上がってきた頃、当時からうちのパジャマを愛用してくださっていた、モデルの鎌田安里紗さんという方に出会いました。その安里紗さんに、「オーガニックコットンは使わないのですか?」と聞かれて。僕はオーガニックコットンは、太い糸でとても切れやすかったり、粗悪なものだと思い込んでいたんです。なので、あまり着心地のいい生地は作れない、という返事をしたんですが、その時の安里紗さんの反応が素っ気なかったんですね。あれ?僕は間違っている?と思って、帰られた後に、オーガニックコットンのことを急いで調べました(笑)。その時僕の思っていたオーガニックコットンのイメージとは裏腹に、既に市場には通常の
コットンと変わらない品質のオーガニックコットンの糸があったんです。
咲(以後 S ) : その当時は私たち、そういうものに興味がなかったんだね、きっと。知ろうともしなかったんだよね。オーガニックコットンのステレオタイプ的なイメージに囚われて。
T: そうだね。その安里紗さんの一言から始まって、GOOD NIGHT SUITのパジャマは2019年に全てオーガニックコットンに切り替えました。
A: その転換はすごいよね。大きな決断と、大きなコストも伴うのに。一人のお客さんの要望に対して、さらっとやり過ごすこともできたのに「こうしなきゃ!」と強く思ったのは何故?
T : インドでは慣行的なコットンの栽培において、35万人もの児童労働があって、コットンの栽培には大量の農薬が使われているんです。コットンの収穫の際にも落葉剤を蒔いたり。その農薬を買うことができずに、自殺をする農家さんや農薬による健康被害が後を絶たないし、もちろん化学肥料も使っているので土や水を汚す。これはだめだ!と思ってオーガニックコットンへのシフトを決めました。

※繊研新聞 電子版より引用
S: 自分達のパジャマの後ろで、誰かが苦しい思いをしている、犠牲になっているのがすごく嫌だと思ったんです。だからその事実を知った時は、やり過ごすなんて出来なかったですね。
A :人としての当たり前の感覚かもしれないけど、企業になってくるとそういうことを大切にすることも難しくなるよね。GNSは自分達の手が届く範囲でやっているからこそ、この大きな決断をできたというのもあるよね。規模が大きくなればなるほど、そういうシフトはとっても難しい。
とはいえ、大きな変化には色々なことが伴うよね。当時、オーガニックコットンのことを知っていたお客様はいたの?
S : 沢山ではなかったですが、待ってました!という声も実際ありました。 とはいえ、当時は勿論、2025年の今でも、一般のお客様は、オーガニックコットンは「肌に良いもの」という観点から選んでいて、生産背景を想像して、だからこそオーガニックコットンを選ぶ、という人はまだ少ないと思う。この業界で働く人も、その認識は薄い気がします。
T : 売る側、企業側にとって「オーガニック」という言葉はマーケティング用語になってしまった部分もありますよね。だから実際、市場にはオーガニックコットンをマーケティングの為に使って売られているものが沢山ある。生育のスピードが速くなるように、とか、虫がつきにくいように、とか、栽培が容易になるように遺伝子組み換えをされたコットンを使って、それがオーガニックコットンと謳っているブランドもあります。あとは生地全体の10%だけオーガニックコットンを混ぜて、オーガニックコットン使用とを謳っている服もある。本当の意味でオーガニックコットンの服を届けたい、と思うなら、そんな風なことは起こらないはずですよね・・。
S : ちなみにこれだけオーガニックが意識されてきてる中で、実はオーガニックコットンというのは、コットン市場の1%に満たないんです。
A: 1%って・・・。消費者は、肌にいいとか、健康にいいとか、自分にとっていいものかどうか?ということをすごく大切にするけれど、オーガニックではないものを作る背景を理解して、その上でオーガニックのものを選ぶということはまだ少ないよね。なんでも簡単に手に入る日本にいると、人や自然を搾取することに慣れてしまう。
S: 自分のためにオーガニックコットンを選んだとしても、その出会いがきっかけで生産背景を考えることにも繋がればいいんですけどね。
A:そうだね。そしてオーガニックコットンの良さに気づけたというのは、この世界につながるチャンスだよね。どうしても、人っていうのは自分と他人の間とか、海の向こう側の見えない世界との間に分断の意識を作ってしまう・・本当は全ては繋がっていて、全て自分に回ってくるのに。 使い捨て用品や、物をすぐ捨ててしまうのも、そのせいで。捨てたら終わり、という意識も、自分と世界の繋がりの感覚の弱さからくるのだと思う。
==========================================
次回は、染色、縫製、ボタン…まだまだ潜むアパレルの闇をどう切り開いていったか。ぜひご覧ください!